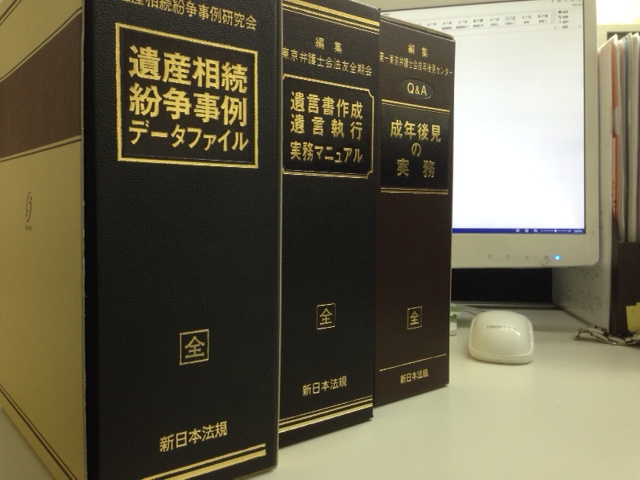オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
2025.10.1
2025.9.29
2025.9.26
2023.9.13
2018.4.6
成年後見制度について
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、ご本人の希望を尊重しながら、財産管理や生活環境を整えるお手伝いをします。
ご本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの類型にわけられます。
後見・・・ほとんど判断することができない
保佐・・・判断能力が著しく不十分である
補助・・・判断能力が不十分である
※医師の診断で判断。
後見人の仕事内容
〇生活・療養看護
①被後見人の介護契約・施設入所契約・医療契約等についての代理権を行使します。
②被後見人の生活のために必要な費用を、被後見人の財産から計画的に支出します。
〇財産管理
①被後見人の財産を管理します。
②被後見人の財産に関する法律行為についての代理権を行使します。
③被後見人の行った法律行為の取消権を行使します。
生活・療養看護
被相続人の財産、収入を把握し、医療費・税金などのきまった支出の概算をし、療養看護の計画を立て、収支の予定を立てます。
被後見人の療養看護は長期にわたることもありますので、中長期的展望に立って、最善の療養看護ができるように計画します。
財産管理
①成年後見人選任の審判があった後、1か月以内に被後見人の財産を調査し、財産目録を作成して、家庭裁判所に送付します。
②被後見人の財産を後見人や第三者の財産と混合してはいけません。
また、被後見人名義の財産を後見人個人の名義にすることはできません。
例えば、税金対策などを理由とする生前贈与等は認めていません。
③被後見人の財産に損害を与えないような安全な方法で管理します。
例えば、株式投資等を行うことは認めていません。
④被後見人の財産から支出できるものは、基本的には、被後見人の生活・療養看護に関する費用です。
⑤被後見人の収入、支出について、金銭出納帳を付け、領収書等の資料を保管します。
また、一定期間ごとに収支のバランスがとれているかチェックします。そして、定期的に家庭裁判所に財産目録を提出して頂く等、後見事務について報告していただかなくてはいけません。
⑥被後見人用居住用不動産について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定などの処分をする場合には、事前に家庭裁判所に「居住用不動産の処分についての許可」の申立てをして許可を得る必要があります。
家庭裁判所による後見監督
家庭裁判所は、被後見人等の利益が十分守られるように、後見等の事務を監督することになっています。そのため、定期的に、あるいは随時、後見等の事務に関し報告を求めたり、調査をしますので、日頃からそれに備えておくことが必要になります。
被後見人等の生活状況の大きな変動(入院、転居等)大きな財産処分、高額な物品の購入、遺産分割等がある場合には、事前に家庭裁判所に連絡し、指示を受けることになります。
後見人の報酬付与
後見人の報酬は、家庭裁判所の審判があってはじめて認められることになりますので、家庭裁判所に「報酬付与」の申立てをする必要があります。被後見人等の財産から勝手に差し引くことはできません。
後見人の任務終了
後見人の任務は後見人等の辞任(家庭裁判所の許可が必要です)解任、後見審判の取消し、被後見人等の死亡により終了します。その時は2か月以内に、後見人等として行った被後見人等の財産管理の計算を家庭裁判所に報告します。
後見人の責任
不適切な財産管理、家庭裁判所の求めた財産目録を提出しない、家庭裁判所の呼出しに応じないなど後見人等として不適任な時は、辞めていただき、家庭裁判所が、第三者専門家を後見人に選任することがあります。
なお、注意義務に違反し、損害が発生した場合は、賠償を求められることがあります。後見人等が被後見人等の財産を使い込むなどした場合、悪質なときは、刑事上の責任を問われることもあります。
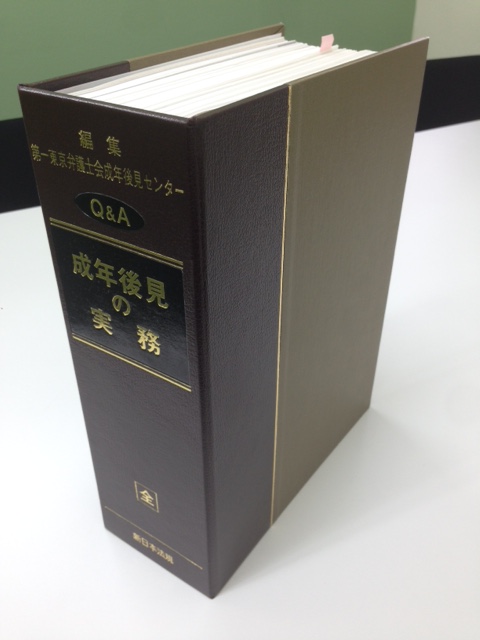
2016.8.24
おはようございます\(^o^)/
まさかの連日投稿、司法書士の泉康生です。
私が今、北京語の家庭教師をつけていることは、昨日のブログでお伝えいたしました。
我が町の天神橋筋六丁目は、最近、外国人で大変賑わっております。
昨日の午後、外国人が駅を出たところで、スマフォを片手に道に迷っておられたので、道を案内するついでに外国人とコミュニケーションをとるチャンスだと思い、元気よく北京語で話しかけましたが、120%通じず、話しかけた自分がパニックに陥るという、大ハプニングがありました!
最終的には、いつもどおり、カタコトの日本語とジェスチャーでご案内いたしました( ̄▽ ̄)
どんまい、俺っ!!
さて、本日のブログのテーマは、「成年後見人のお仕事の身上監護って何??」でお送りいたします。
そもそも、成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神的疾病などにより必ずしも判断能力が十分ではない方(本人)について、その権利や財産を守り、本人を支援する制度をいいます。
例えば、預貯金の解約、保険金の受領、不動産の売買などを行うには、その行為をすることによって、自分がどのような利益を受け、どのような不利益を被るかを十分理解する必要がありますが、本人自身がそうした判断ができないか、援助が必要な状況にある場合には、本人の代わりに判断したり、本人を援助したりする人を決める必要があるのです。
成年後見人のお仕事は大きく分類すると、「財産管理」と「身上看護」の2つに分けることができます。
このうち、成年後見人が負う身上監護義務は、事実行為に関するものではなく、法律行為に関するものです。
言葉が難しいですね。
簡単に申し上げると、成年後見人が自ら、日々本人の介助を行うものではなく、家事代行の手配が必要であれば家事代行のサービス会社等と契約を締結したり、適正な医療や福祉サービスが受けられるよう、関係機関と契約を締結するなどの行為を行ないます。
本人が在宅の場合と、施設に入所している場合とで、身上監護の内容も変わってきます。
実際、このあたりはとてもデリケートな問題ですので、成年後見人は、常に、「本人にとって何が一番良いのか」「本人はどのような生活を望んでいるだろうか」を推察し、本人の資産状況や健康状態等の要素も考慮して、判断していく必要があります。
以上です。
成年後見人のお仕事は、簡単なお仕事ではありません。
でも、とてもやりがいのあるお仕事です。
今後も積極的に取組んで参ります!
というわけで、みなさん、今日も素敵な一日をお過ごしください♪
司法書士 泉 康生
.jpg#_uploads_akamonlink)
2016.8.15
家族信託コーディネーターの泉 喬生です。
今回は、成年後見制度について書いていきます。
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて決定されます。
法定後見制度においては、本人が精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
・後見とは
精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。(但書きは、保佐・補助共通)
・保佐とは
精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
・補助とは
軽度の精神上の障害により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、不動産を売買するなど特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
...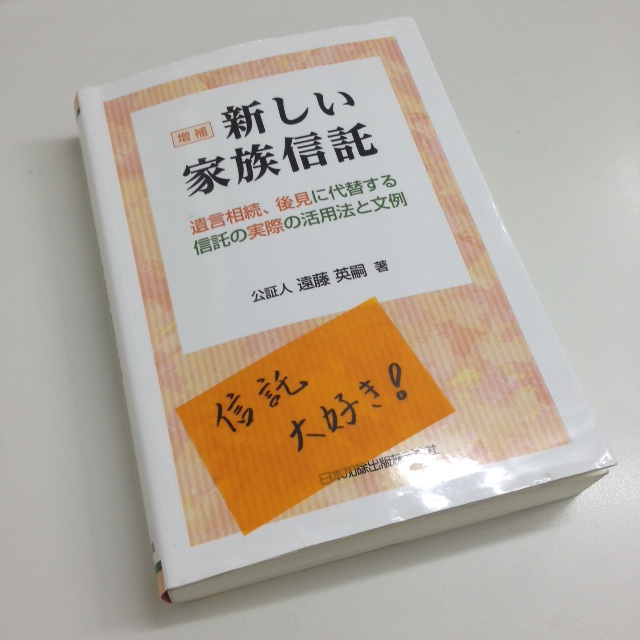
2015.3.19
おはようございます!!
雨の音がけっこう好きな司法書士の泉です♪
まさかの3日連続のブログ更新で、私自身、たいへん驚いております。
さて、本日のテーマは、もちろん!
「成年後見と信託」
です。
私は今、成年後見業務に取り組んでいます。現在は、10名の方の成年後見人に就任しております。
また、某社会福祉協議会の法人後見の委員会にも所属しております。
司法書士になってから今まで、数多くの個別案件に関わらせていただきました。
私が成年後見人に就任することになったきっかけは、
「不動産の売却」
でした。
不動産を売却できるのは、不動産の所有者です。
「居住者」でもなければ「所有者の息子さん」でもありません。
不動産の所有権を有している方が「使用」「管理」「活用」「処分」「保存」等を自由に行うことができるのです。
では、もしその所有者が認知症になってしまったらどうでしょうか?
「使っていない土地を売却して、今後の生活費に充てたい。」
「施設に移る際の費用に充てたい。」
「管理がめんどくさいから売却したい。」
「将来の相続対策をしたい。」
このようなときに、何ができるでしょうか。
残念ながらこのままでは何もできません。
成年後見制度を利用しない限り、何もできません。
ただ、成年後見制度を利用しても「将来の相続対策」はできません。
成年後見制度は、あくまでもご本人さんの財産を保全するための制度だからです。
ポイントは「判断能力の有無」「判断能力の程度」です。
先ほどのケースで、不動産の名義人である所有者が、不動産を売却したいけど既に認知症等で「判断能力が欠けている」状態と判断されれば、管轄の家庭裁判所に「成年後見人選任の申立て」を行い、成年後見人が選ばれたあと、その成年後見人が本人に代わって、不動産を売却することになります。
また、居住用の不動産の売却にあたっては、別途「裁判所の許可」が必要なのです。
実際に私も、数件、このような手続きで不動産を売却しました。
なんせ、時間がかかります。
成年後見人の選任申立てから不動産の売却まで、手続上、どうしても2〜4ヶ月はかかります。
でも、ご本人さんの大切な財産を処分するわけですから、当然とも言えますよね。
では、こういうことは可能でしょうか。
「もし、私が認知症になっても、A(息子さん)の判断で、この不動産を売却してくれ。」
どうでしょうか。いつもブログを見て下さっている税理士の吉田さん、どうですか?
吉田さん「ん〜認知症になったらできないんじゃないでしょうか。」
泉「可能です!」
吉田さん「えぇ〜!!」
泉「行政書士の岡本さん、これを踏まえてどうですか?」
岡本さん「ん〜できないんじゃないでしょうか〜。」
泉「可能です!」
岡本さん「えぇ〜!!」
そうなのです。民事信託ならこれを実現することが可能なのです。予め、
「この不動産の管理処分する権限をAに託す」
「私の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付して幸福な生活及び福祉を確保するため、必要に応じて、この不動産を管理処分してくれ」
と、元気なうちに(判断能力があるうちに)決めておくことができるのです。
「これで将来収益マンションを建築してくれ」
と言って、数億円、信託することも可能です。
信託銀行に託すのではありません。信頼できるご家族の方に託すのです。
信託の特徴を活用することで、今まで「民法」ではできなかったことが、実現できるのです。
信託ってすごい!!
信託の構築にあたっては、法律的なことはもちろん、税務的にも慎重に行なわなくてはなりません。本当に慎重に行う必要があります。
なんでもご相談ください!!
みなさまの想いをカタチにするのが、私の仕事です。
本日は以上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪
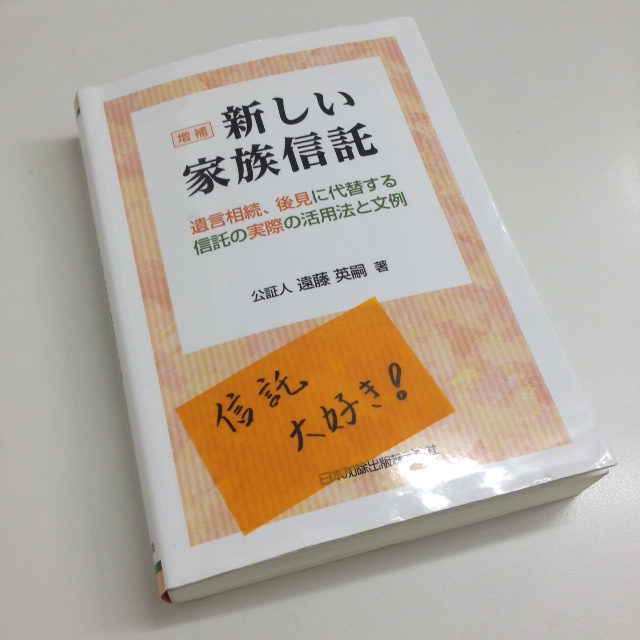
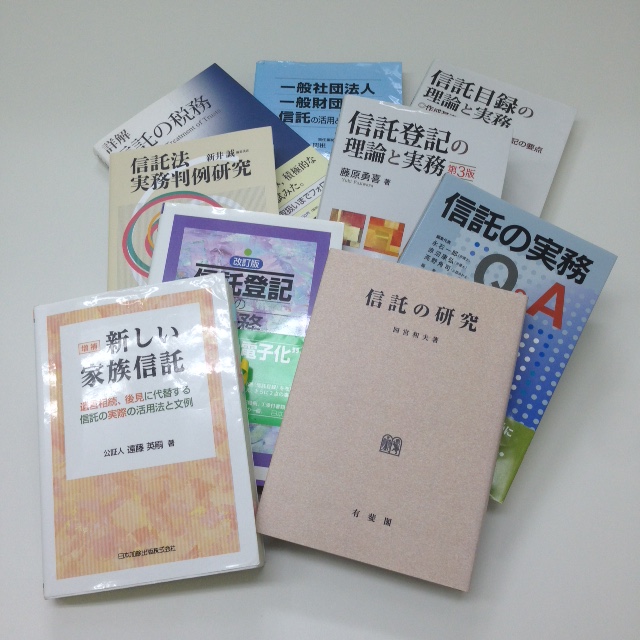
2015.3.18
おはようございます!元気すぎて4時に目覚めた司法書士の泉です!
いつもより30分早めの行動で、今日も絶好調です♪
3月、、、
やるやないか。
く、く、く、く、、、、
挫けるわけないやん( ´ ▽ ` )ノ
時間管理・自分管理で、自分との闘いに負けるわけがありません( ̄▽ ̄)
ドンと来いこのヤローo(`ω´ )o
ありがたいことに、不動産登記のお仕事も入ってきました(≧∇≦)
紹介料を一切支払わない私にこうやってお声をかけていただけること、本当にありがたく思います!
そして、今まで携わらせていただいたクライアントからのお問合せ、、、
感無量とはこのことです!!
さて、今日は信託のお話です。
以前、将来の認知症に備えて、不動産の管理処分する権限をご家族の方に託す、信託手続きをさせていただきました。
不動産の信託でしたので、信託登記もさせていただきました。
そして、なんと、クライアントから「無事にその不動産の買い手が見つかった」との報告をいただきました。
しかも良い条件で売却できたようで、クライアントも大変喜んでおられました。
不動産の売却にあたっては「売るタイミング」が非常に重要だと思います。
所有者がご高齢の場合「認知症」になるリスクは統計的に見ても高くなります。
認知症になると、所有不動産を売却する必要性が生じても、成年後見制度を利用しなければ売却できません。また、居住用不動産の売却にあたっては「裁判所の許可」も必要となります。
そのため、売却を急ぎ、通常より安値で売却せざるを得ない、という事態にもなりかねません。
今回もそのようなリスクを回避するため、信託を提案し、契約をしました。
そのおかげで、売却を焦ることもなく、最高のタイミングで売却できたのが良かったです。
信託は本当におもしろい!
そして奥が深い!
不動産の管理・処分・承継については、必ず専門家にご相談ください。
そして、最後に私にご相談ください。
「信託」はまだまだ事例が少ないです。でも、クライアントの想いを実現するためには「信託」の知識は必要不可欠です。
実際に、私は今まで500件以上の将来の財産管理に関する相談を受けて参りました。
そして「相続」「遺言」「成年後見」業務に今まで力を入れてきたからこそ、それらの制度の限界を、身をもって知りました。
「遺言書を作成したことがあるから、遺言書の相談には乗れる」
「成年後見人になったことがあるから、財産管理の相談には乗れる」
これだけじゃダメなんです!
これだけの知識では、できる提案がどうしても限られてしまうのです。
「信託で実現できること」
「信託でしか実現できないこと」
がたくさんあります。
『不動産の管理・処分・承継』
これは本当に大切な問題です。
現実から逃げることなく、きちんと向き合い、考える必要があります。
一緒に考えましょう!!
私にしかできない提案がある、と、今なら自信を持って言えます。
本日は以上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
不動産の管理・処分・承継に関するご相談は、泉司法書士事務所にお任せください!
アイラブ信託法の司法書士の泉でした♪♪
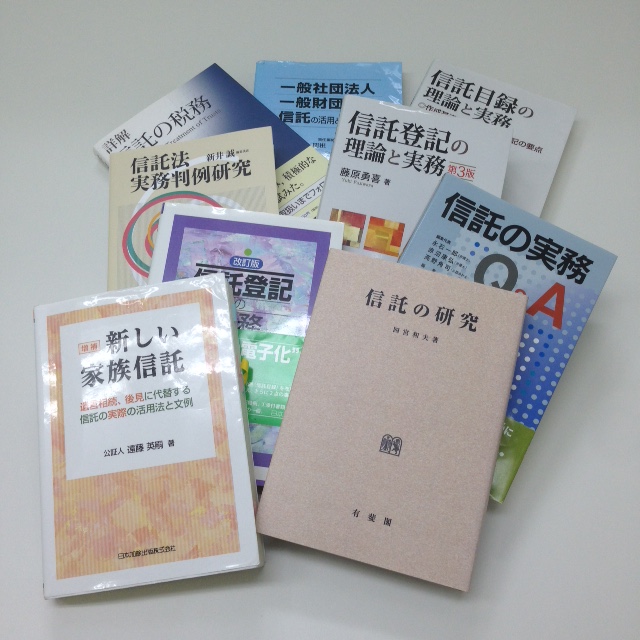
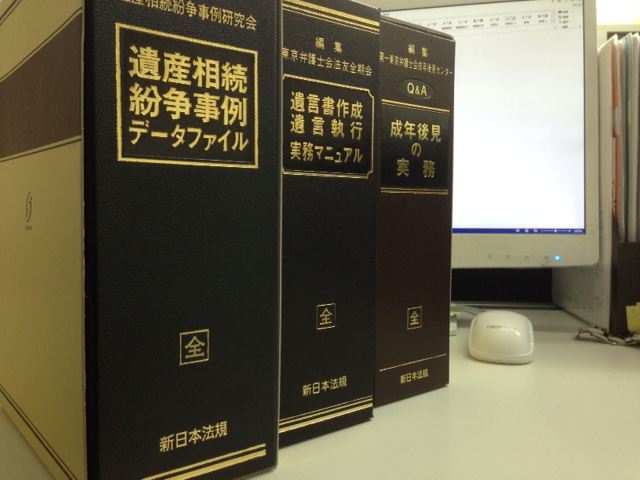
2015.3.10
おはようございます!
実は火曜日が苦手だった司法書士の泉です!
最近やっと気づきました。
私、火曜日が苦手だったのです。
これに気づいたとき、「なるほどなー」って、、、、
どうでもええわっ!
さて、本日のテーマはこちら!
「成年後見と遺言」
です。今まで、数多くの『成年後見業務』『遺言書作成支援業務』に携わらせていただきましたが、「成年被後見人の遺言書」はまだやったことがありません。
しかし、今回、クライアントからちょっと相談を受けましたので、思いっきり調べました。
そもそも「成年被後見人に遺言書が作成できるのか」と思われがちですが、それはできます。
こちらの規定をご覧ください。
【民法第961条】
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
【民法第973条】
1 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
です。
眠たくなりましたか?起きていますか?おはようございます!
つまり、民法は成年被後見人の遺言書を認めているのです。
「遺言は、自然人の最終的な意思であり、できる限り尊重すべき」
というのが理由です。
裁判例もたくさんあります。
ポイントは「遺言書の内容を難しくし過ぎない」ことですね。
プロとしての腕の見せ所です。
もちろん、通常の遺言よりも後日相続人間で「遺言をする能力」について争われる可能性が高いと言えますので、遺言作成時の状況・医師の判断等を書面やビデオ、テープなどで可能な限り証拠として残しておくことが必要ですね。
「遺言」は本当にデリケートです。
人の死はいつ訪れるか誰にもわかりませんから。
私が常に心がけているのは、面談時に「これがこのクライアントの想いだ」と確信したら、その場で自筆証書遺言を書いてもらうこと。
後悔して欲しくないし、後悔したくないから。
「想いをカタチにする」のが私の仕事。少しでも可能性があるのであれば、トコトン調べてチャレンジします。
それがクライアントの想いですから。
本日は以上です。 いや〜こんな時間からこんなアツいブログを書くなんて思ってもみなかったー!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
熱血司法書士の泉でした!